2024.09.30
制作会社・芸能プロダクション(エンタメ業)でよくある労務トラブルと知っておくべきポイントについて弁護士が解説
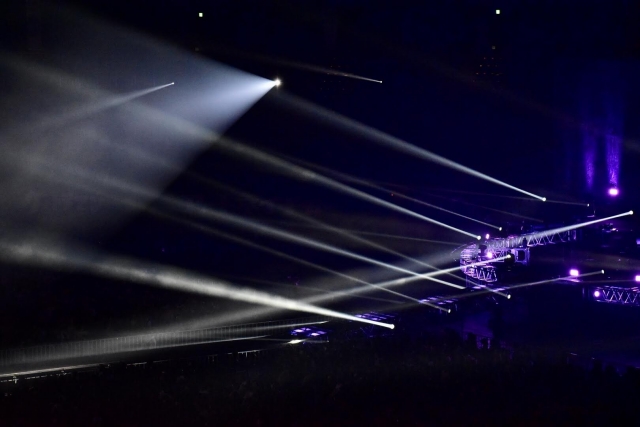

三浦 裕和
弁護士困っている人が、気軽に相談できるよう、依頼者の話をよく聞き、依頼者に寄り添う弁護士でありたいと考えています。
悩みや問題を抱えていらっしゃるときは、まずは相談にきてみてください。誠心誠意お話を聞かせていただき、全力で対応させていただきます。
1 エンタメ業(芸能関係)とは?
エンターテイメント業界(エンタメ業)とは、映画、音楽、テレビ、動画、ゲーム、アミューズメントなど、人々に娯楽を提供する産業のことです。
最近では、IT化がすすみ、AIが発展することで、元々消費者側であった人々がエンタメを提供する側(YouTuber、VTuber等)になることで、エンタメ業界の裾野が広がりつつあります。加えてコロナ禍の巣ごもり需要により、一部のエンタメ業界はその需要を伸ばし続けています。
2 エンタメ業(芸能関係)を取り巻く現状
公益財団法人日本生産性本部が発表する「レジャー白書2023」によると、動画等のコンテンツ配信は堅調に伸び続け、コロナ禍により一時的に減ったシアター系の鑑賞レジャー(コンサートや映画など)も、コロナ禍前の水準に回復してきました。
また、同調査によると、「仕事よりも余暇の中に生きがいを求める」と回答する人が増加し続けています。
余暇を楽しく過ごすために、エンタメ業への需要は非常に高まってきているといえるでしょう。
3 エンタメ業(芸能関係)特有の労務問題
エンタメ業界での仕事は、一見すると華やかな仕事に見えますが、華やかだけではなく、様々な労務トラブルを抱えています。
エンタメ業界では、傾向として夕方以降に仕事が入ることが多くあり、長時間かつ不規則になりがちです。
また一つの作成を完成させるまでに多くの人が関わり、比較的短い納期での仕事の完成が要求されることも多いため、仕事が夜遅くにまで及ぶことが少なくありません。クリエイティブな業界ではよく見られることですが、時期や日によって業務内容や業務量が大きく変わりやすく、長期的な予測がつきにくい職種といえます。
したがって、エンタメ業を営む会社(芸能プロダクション・制作会社など)は、不規則かつ長時間になりがちな業務を、適切に労務管理をしていく必要があります。
4 エンタメ業(芸能関係)で発生しやすい労務トラブルその1~契約形態のトラブル~
(1)契約形態(労働契約か業務委託契約か)
通常、会社がその会社の事業に従事させる場合、労働契約を締結することが多いですが、エンタメ業界ではフリーランス人材との間で「業務委託契約」の形式で契約を締結することが多々あります。
フリーランス人材との契約は、会社がその人材を従業員として雇うのではなく、対等な関係で契約を締結することを前提とします。会社としては、フリーランスの人材が行う業務に対して報酬を支払えば足り、フリーランスの人材が遅い時間まで仕事を行っても、残業代の支払義務が発生しないというメリットがあります。
そのため、フリーランス人材と契約する会社のなかには、実態は「労働契約」であるにもかかわらず、従事者との間で「業務委託契約」を締結して労務管理や残業代の支払いを免れようとする会社もあります。
しかし、労働基準法上、たとえ契約の名目が「業務委託契約」であっても、その仕事をしている実態が「労働契約」であれば、労働基準法の適用があります。
そして、実態が「労働契約」であると判断されれば、過去に遡って残業代を支払わなくてはいけなくなります。
また、芸能事務所では、所属するタレントに対して「専属マネジメント契約」という名目で契約することが一般的ですが、名目上「専属マネジメント契約」であっても、業務委託契約と同様にその実態が労働契約であれば、労働基準法の適用を受けることになります。
そのため、エンタメ業を営む会社が、「業務委託契約」「専属マネジメント契約」などを締結する際は、その実態が「労働契約」に該当しないように注意する必要があります。
(2)「労働者」に該当するか否かの判断基準
では、どのような場合に「労働契約」に該当すると判断されるのでしょうか。
この判断基準が明確であればエンタメ業を営む会社が注意しなくてはならない事項が明確になりますが、残念ながら「労働契約」にあたるか否かの明確な判断基準はありません。
そのため、どのような場合に「労働契約」に該当するか否かは、行政の研究や「労働者」性を判断した過去の裁判例を検討する必要があります。
(ア)行政の研究
行政の研究としては、1985年に労働省労働基準法研究会報告があります。同報告では、従事者が「労働者」に該当するか否かについて、以下の判断基準が示されており、裁判例でも「労働者」に該当するか否かの考慮事情として広く利用されています。
(イ)裁判例
芸能プロダクションと、そこに所属する歌手Aとの間の「マネジメント専属契約」が、労働契約であるか争われた結果、当該マネジメント専属契約が、実質上労働契約と判断された裁判例(東京地裁平成28年3月31日(判タ1438号164頁))を一つ紹介します。
同事件は、
① 本件契約期間中,同芸能プロダクションの専属芸術家として、同芸能プロダクションのためにのみ出演業務等を行うという契約であり、同芸能プロダクションの承諾なくして他に芸能活動を行うことができないこと(業務遂行上の指揮監督、専属性)
② 歌唱,演奏等の録音・録画,放送等の一切の利用が芸能プロダクションに対してのみ許諾され、芸名に関する権利は全て原告に帰属すること(Aに事業性がない)
③ Aは芸能プロダクション又は第三者の企画への出演業務,楽曲の制作,録音録画物などの制作のために芸能プロダクションの指示に従って活動しなくてはならないこと(業務従事の指示等に対する諾否の自由がない)
④ 芸能プロダクション側は,Aの出演業務等の遂行から生じる著作権上の全ての権利等を独占的に取得するとともに,芸能プロダクションの出演業務等に対する対価を全て取得し,Aは,原告から活動ごとに一定割合の支払を受けるにすぎないこと(Aに事業性がない)
⑤ Aの実際の活動も,芸能プロダクションの方針に基づき,芸能プロダクションを通して出演等業務の依頼を受け,Aはこれを断ることなく歌唱,演奏の労務を提供し,各歌唱,演奏活動にあたっては,演目や衣装等の内容面にもわたってマネージャーの指示を受けた上,開始時間や終了時間を報告し,Aが受領した売上は全て原告に送金していたこと(業務従事の指示等に対する諾否の自由がない、報酬の労務対象性)
を考慮して、会社とタレントの間の「マネジメント専属契約」が労働契約に該当すると判断しました。
5 エンタメ業(芸能関係)で発生しやすい労務トラブルその2~残業代トラブル~
エンタメ業界では、不規則労働・長期間労働が常態化していますので、少しでも残業代の支払額を減らすために、「裁量労働制」や「事業場外みなし労働時間制」を導入する会社が多くあります。
裁量労働制や事業場外みなし労働時間制が適用されれば、基本的には実労働時間にかかわらず、みなし労働時間に対する給料を支払えば足りることになります(もっとも、深夜労働・休日労働の規制は受けます)。
しかし、これらの制度を導入するためには職種や条件に明確な要件があります。
実際、大手芸能事務所などで、本来上記制度の対象にならない従業員に対して、裁量労働制や事業場外みなし労働時間制を適用させて、残業代を支払わずに長時間労働を行わせていたとして、労基署から指導を受けるということが発生しました。
そのため、エンタメ業を営む会社が「裁量労働制」「事業場外みなし労働時間制」を導入するためには、同制度の導入要件を満たし、かつ、条件を満たす業務を従業員に対して課しているのか、注意をする必要があります。
(1)裁量労働制
業務の性質上、労働者に対して労働時間や業務の遂行の方法について大幅な裁量を持たせる必要性がある業務について、労働者が実際に仕事をした時間と関係なく、労使協定で定めた時間労働したものとみなす制度です。
裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」の2種類がありますが、エンタメ業界では、主に「ゲームソフトウェアの創作業務」「放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー、ディレクターの業務」に従事する労働者に「専門業務裁量労働制」の適用が考えられます。
もっとも、同制度は、その名前のとおり、適用される従業員に大幅な裁量があることが本制度の適用の要件となっています。
そのため、「ゲームソフトウェアの創作業務」に従事している労働者でも、その具体的な業務内容が専ら他人の具体的指示に基づく裁量権のないプログラミング等を行う者には同制度を適用できません(「専門業務型裁量労働制の解説」7頁)。
また、「放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー、ディレクターの業務」プロデューサーやディレクター業務については、以下のように規定されています(「専門業務型裁量労働制の解説」6頁)。
(参考:厚生労働省『専門業務型裁量労働制の解説』)
定義上、明確な業務内容が記載されているわけではありませんが、労働内容や決定について大幅な裁量が認められることが前提となるため、業務上の指揮監督を受けて行動する従業員に対して「プロデューサー」「ディレクター」という名称を与えたとしても、「専門業務型裁量労働制」を適用することはできず、時間外労働規制の適用を受けることになります。
なお、上記制度をエンタメ業を営む会社が採用するためには、労使協定で制度の対象とする業務やみなし労働時間など様々な事項を定める必要があります。それに加えて、個別の労働契約や就業規則を整備して、所轄の労働基準監督署に協定届の届け出を行い、労働者本人の同意(令和6年4月1日以降は専門業務型裁量労働制を採用するにあたっても必要)を得る必要があります。
(2)事業場外労働時間制
事業場外労働時間制は、労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事したときに、その労働時間を算定し難い場合、所定労働時間又はその業務の遂行に通常必要とされる時間外労働したものとみなす、という制度です。
事業場外労働時間制を採用するためには、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な業務に限られます。
そのため、以下のような業務状況の場合は、同制度を適用することはできません。
・携帯電話やスマートフォンによって、随時指示を受けながら事業場外で労働している場合
・事業場において、訪問先、帰宅時刻等当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後、事業場に戻る場合
(参考:厚生労働省『「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適正な運用のために』)
(3)固定残業代制
固定残業代は、その名称から固定残業代を支払えば、残業代の支払いを免れるかのように見えますが、実際は、固定残業代の対象とされた時間外労働時間を超過した場合は、残業代を支払う必要があります。
さらに固定残業代が残業代の支払いと認められるためには、基本給と固定残業部分が明確に区別でき、かつ、残業の対価として支払われているという実態がある場合に限られます。同要件を満たさない場合は、固定残業代とされた部分は基本給に含まれるとして残業代の計算がなされる可能性があります。
6 エンタメ業(芸能関係)で発生しやすい労務トラブルその3~転職時・独立時のトラブル~
(1)競業避止義務
エンタメ業界では、従事者が退職や転職をする際、その条件について様々なトラブルが発生することがあります。
エンタメ業を営む会社は、その性質上、人材を育成するために多額の費用を掛けざるを得ないことが多々あります。特に、契約者が芸能人である場合は、会社がかなりの時間や費用をかけて、プロモーションを行っていることも多いでしょう。
エンタメ業を営む会社としては、その投資した費用を回収する前にその人材が転職や独立をしてしまうと非常に損をすることになりますので、競業避止義務を記載した誓約書を作成することがあります。
しかし、会社が個人に対し過剰な競業避止義務を課すことは、退職者の職業選択の自由や営業の自由を不当に制限することになってしまいます。
そのため、裁判例上、競業避止義務の程度・期間・代償措置などを考慮して、その制限が公序良俗に反するほど過剰と言える場合は、競業避止義務の効力を無効と判断することがあります。
【エンタメ業界で競業避止義務の有効性を判断した裁判例】
東京地裁令和4年5月31日判決(出典:ウエストロ―ジャパン)
同事件は、ゲームソフトのバグを検出する業務を行う会社である原告が、原告企業を退職した元従業員Bに対して、競業避止義務違反を理由に損害賠償請求をした事案です。
原告企業の業務は、制作会社等から委託を受け、ゲーム等のソフトウェアが仕様どおりに動作するかを確認し、プログラムの不具合の有無を検出するテストを行うことで、原告は、Bが退職をする際、以下の内容の退職時誓約書を作成していました。
退職時誓約書(抜粋)
「私は、貴社を退社するにあたり、2年間貴社の許可なく次の行為をしないことを誓約いたします。また、本誓約に違反し、貴社に損害を与えた場合は責任をもって賠償致します。
1 貴社と競合関係にある事業者に就職又は役員に就任すること
(中略
4 名目の如何を問わず、また、直接・間接を問わず、貴社との競合関係を発生させる活動を行う事
同事件では、上記条項が公序良俗に違反するか争ったところ、以下の理由で上記の退職時誓約書の競業避止義務に関する規定が、公序良俗に反する条項と判断されました。
① 本退職誓約書の合意は、被告Bが、原告と競合関係にある事業者に就職又は役員に就任することだけではなく、「名目の如何を問わず、また、直接・間接を問わず」(4項)原告との競業関係を発生させる活動を行うことを禁止するものであるため、被告Bに対し、原告との競業関係を発生させるあらゆる活動を禁止したものと解するほかない
② 原告の業務はソフトウェアのテスト業務であるから、同合意は、テスト業務に関わるあらゆる活動を禁止したものということになる。
③ 被告Bは、原告に就職する前からソフトウェアのテスト業務に従事していた者であり、原告に在籍している間も同業務に従事していたのであるから、原告退職後ソフトウェアのテスト業務に関わるあらゆる活動が禁止されるとなると、それまでの職業生活で得た知識や経験を活かすことが不可能になり、その職業選択の自由等が制限される程度は極めて大きい。
④ 原告において、被告Bが負う不利益を緩和するために何らかの代償措置がない
⑤ したがって、競業避止義務を課される期間が退職後2年間に限定されていること等を考慮しても、上記合意は、被告Bの職業選択の自由等を過度に制約するものであって、公序良俗に反して無効であるといわなければならない。
(2)芸名の使用について
芸能人と契約を締結している芸能プロダクションにおいては、タレントに対して、特に多額の費用や労力(マネジメント等)を投資していることから、その投下した資本の流出を防ぐため、転職・独立後の「芸名」の使用を制限する合意を締結する会社があります。
しかし、前述の競業避止義務と同様に、過剰に権利を制限するものは、公序良俗に反する規制として、無効になることがあります。
【芸名の使用を制限する規定の有効性について判断をした裁判例】
(東京地裁令和4年12月8日(判タ1510号229頁))
同事件は、芸能プロダクション(原告)が、所属していたタレント(被告C)に対して、以下の条項が専属マネジメント契約に含まれることを理由に、芸名の使用の差し止めを請求した事案です。
契約書の内容(抜粋)
第8条 被告の出演業務により発生する著作権、著作隣接権、著作権法上の報酬請求権ならびにパブリシティ権、その他すべての権利は、何らの制限なく原始的に原告に帰属する。
第10条 被告は本契約期間中はもとより契約終了後においても、原告の命名した以下の芸名および名称を原告の承諾なしに使用してはならない。
同事件では、パブリシティ権の譲渡性自体は否定しませんでしたが、「①それによって原告の利益を保護する必要性の程度、②それによってもたらされる被告の不利益の程度及び③代償措置の有無といった事情を考慮して、合理的な範囲を超えて、被告の利益を制約するものであると認められる場合には、上記部分は、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効になる」との判断基準を示したうえで、具体的には以下の理由から、第8条規定のパブリシティ権に係る部分を無効になると判断し、そのうえで第8条のパブリシティ権に係る部分の効力を実質的に認めることになる第10条の契約終了後の芸名の使用制限の条項の効力を否定し、芸名の使用の差止請求を棄却しました。
① 原告による投下資本の回収は、基本的に原告と被告Cとの間で適切に協議したうえで、合理的な契約期間を設定して、その期間内に行われるべき
② 同規定のパブリシティ権に関わる部分は、被告Cが、原告の所属から離れた場合に、自らの活動の成果が化体した芸名を原告の許諾無しに芸能活動に使用できなくするものであり、実質的に原告の所属から離れて芸能活動をすることを制約する効果を有し、さらには、契約期間終了後の自由な移籍や独立を委縮させる効果を有する
③ 芸名に顧客誘引力があるため、同条項による被告Cへの不利益の程度が大きい
④ 代償措置の定めがない
以上を理由に、「第8条のパブリシティ権に係る部分は、原告による投下資本の回収という目的があることを考慮しても、適切な代償措置もなく、合理的な範囲を超えて、被告の利益を制約するものであるというべきであるから、社会的相当性を欠き、公序良俗に反するものとして無効になる」として、芸名使用の差止請求を棄却しています。
7 その他エンタメ業(芸能関係)の労務問題
(1)未成年への仕事の依頼
エンタメ業界のなかでも、タレントや歌手といった芸能関係の仕事は、未成年が演じる必要性があることがあります。
労働法上、使用者は、中学校を卒業する前の児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者)を使用してはならない(労働基準法56条1項)と定められていますが、映画の製作又は演劇の事業については、子役の必要性から満13歳に満たない児童についても、就学時間外に使用することが認められています。
加えて、極めて例外的な場合ではありますが、以下の4要件を満たす場合は、中学校を卒業する前の児童であっても、そもそも「労働者」に該当しないと判断されています(昭和63年7月30日基収355号)。
①当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。
②当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。
③リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあってもプロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。
④契約形態が雇用契約ではないこと。
(2)労災の加入
エンタメ業界のなかでも以下の芸能従事者については、令和3年4月1日以降、「労働者」に該当しなくても労災保険に特別加入することができるようになりました。
(ア)芸能実演家
・俳優(舞台俳優、映画及びテレビ等映像メディア俳優、声優等)
・舞踊家(日本舞踊、ダンサー、バレリーナ等)
・音楽家(歌手、謡い手演奏家、作詞 家、作曲家等) ・演芸家(落語家、漫才師、奇術師、 司会、DJ、大道芸人等) ・スタント 他
(イ)芸能製作作業従事者
監督(舞台演出監督、映像演出監督) ・撮影 ・照明 ・音響・効果、録音 ・大道具製作(建設の事業を除く) ・美術装飾 ・衣装 ・メイク ・結髪 ・スクリプター ・ラインプロデュース ・アシスタント、マネージメント 他
(参考:厚生労働省『芸能従事者の皆さまへ』令和3年4月1日から労災保険に特別加入できるようになります)
8 フリーランスの人材との契約
(1)独占禁止法の問題
ここまでは「労働者」との間の労務トラブルについて説明してきましたが、従事者との間の契約の形式及び実態が「労働契約」に該当しない場合でも、その契約内容が、「独占禁止法」違反にならないように注意する必要があります。
公正取引委員会の令和元年9月25日の「人材分野における公正取引委員会の取組」では、エンタメ業界の「フリーランス」の人材と会社との間の関係について、優越的地位の濫用・取引妨害の防止の観点から、以下の場合が独占禁止法上、問題になる可能性があると報告されました。
(参考:公正取引委員会『人材分野における公正取引委員会の取組』(令和元年9月25日))
また、同報告では、問題があるとまでは記載されませんでしたが、競争政策上、望ましくないものとして、「契約等を書面によらず口頭で行うことは、優越的地位の濫用等を誘発する原因となり得るため、望ましくない」と報告されました。
(2)フリーランス・事業者間取引適正化等法
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が、令和5年4月28日に成立し、同年5月12日に公布されました(施行日はまだ確定していませんが、令和6年秋ごろまでに施行が予定されています)。
そのなかで「60日以内の報酬支払期日の設定」(同法4条1項)「募集情報の的確表示」(同法12条)「継続的業務委託に対する中途解約」(同法16条)に関する規定が定められました。
9 弁護士依頼
ここまでご説明してきたとおり、エンタメ業界で働く人材との間の契約内容や業務の依頼については、非常に難しい問題があります。そして、エンタメ業界は、注目度が高い業界ですので、法的なトラブルが発生すると社会的な評判を傷つけることにもなりかねません。
これらの問題に対して、懸念がある場合や紛争が発生してしまった場合は、弁護士にご相談ください。

三浦 裕和
弁護士困っている人が、気軽に相談できるよう、依頼者の話をよく聞き、依頼者に寄り添う弁護士でありたいと考えています。
悩みや問題を抱えていらっしゃるときは、まずは相談にきてみてください。誠心誠意お話を聞かせていただき、全力で対応させていただきます。














①使用者従属性の有無
・ 仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
・ 業務遂行上の指揮監督の有無
・ 勤務場所及び勤務時間の拘束性の有無
・ 他人による業務の代替性の有無
②報酬の労務対象性(報酬が時間単位か否か)
③補強する事情(事業者性の有無・専属性の程度など)
(参考:厚生労働省『労働基準法研究会報告』(労働基準法の「労働者」の判断基準について/昭和60年12月19日)